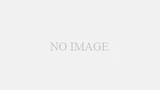こんにちは。タキです。
近年、投資に対する意識の高まりが感じられますね。とてもいいことだと思います。
NISAやiDeCoなどの制度で国が後押ししていますし、最近では投資に関するニュースもよく見かけるようになりましたね。
2022年からは高校の金融教育が始まって、資産形成やライフプランニングについて教えてもらえるそうですよ!
しかし、日本では投資をしている人はまだまだ少数派です。
そこで、今回のテーマは「なぜ投資をしないといけないのか」です。
【投資とは何か?】
まず、そもそも投資って何なの?という根本的な話からしていきます。
皆さんなんとなくイメージはついていると思うのですが、
【なぜ投資をしないといけないのか?】
■インフレ(物価は上がっているのに給料は上がってないし税金や社会保険料は増えてる)
投資をしないといけない1つ目の理由は、インフレです。
インフレとは物価上昇のことですね。
昨今はインフレがひどく、食料品やガソリンなど本当に値上がりしたなと感じるものがたくさんあります。
あまりピンとこないかもしれませんが、物価が上がるということは、相対的に通貨の価値が下がっていることを意味します。
スーパーで例えてみると、1万円で買える商品の量は、現在と皆さんが子供の頃とでは全然違いますよね。
現在は、昔と比べて多くの商品が値上がりした結果、同じ1万円でも買える量が減ったのです。
これは相対的に通貨の価値が下がったということに他なりません。
今後は、同じ1万円という額でも、買えるものはどんどん減っていってしまうのです。
マクドナルドのハンバーガーは現在(2025年4月5日時点)1個190円になってしまいました。
昔はハンバーガー1個60円くらいの時代もあったんですけどね。
そして問題は、貯金はインフレに弱いということです。
2024年の物価上昇率は3%だったみたいですね。
ということはお金の価値も3%下がっています。
額面上は変わらなくても、物価が上がると通貨の価値が下がるので、貯金は目減りしていくということです。
一方で預金金利なんてスズメの涙。定期預金でも貰える利息は物価上昇率以下です。
物価上昇以上の利息を貰えないと、貯金はどんどん目減りしていってしまいます。
つまり、貯金は目減りしていくので、投資をして物価上昇率以上に資産を増やさないといけないよということです。
・物価は基本的に上がり続ける
その大きな要因は圧倒的な人手不足と国力低下による円安とマネーストックの増加
短期的に為替の動きは分からないが、長期的に見ると円安の傾向が大きいのではないか。
少子高齢化はインフレ要因となる
今後も物価は上がっていくことを想定しておかないといけません。
そして、今後は人手不足も相まってかなりのインフレが起こる可能性があります。
つまり、インフレを考慮すると投資をやらないといけないよ、ということです。
■将来への備え(減っていく年金)
投資をしないといけない2つ目の理由は、将来(主に老後)のための資産形成です。
日本には年金制度があり、高齢者の多くはこの年金によって生活を賄っています。
しかし、この年金は今後の持続可能性が危ぶまれている制度でもあります。
年金は、働いている現役世代が納める保険料で成り立っている(賦課方式と言います)ので、
今後は少子高齢化により現役世代が減って、もっと厳しくなるだろうと言わざるを得ません。
少なくとも支給額が減額されることはほぼ確定です。
厚生労働省の推計では、30年後には2割程度給付額は減っていくだろうと試算しています。
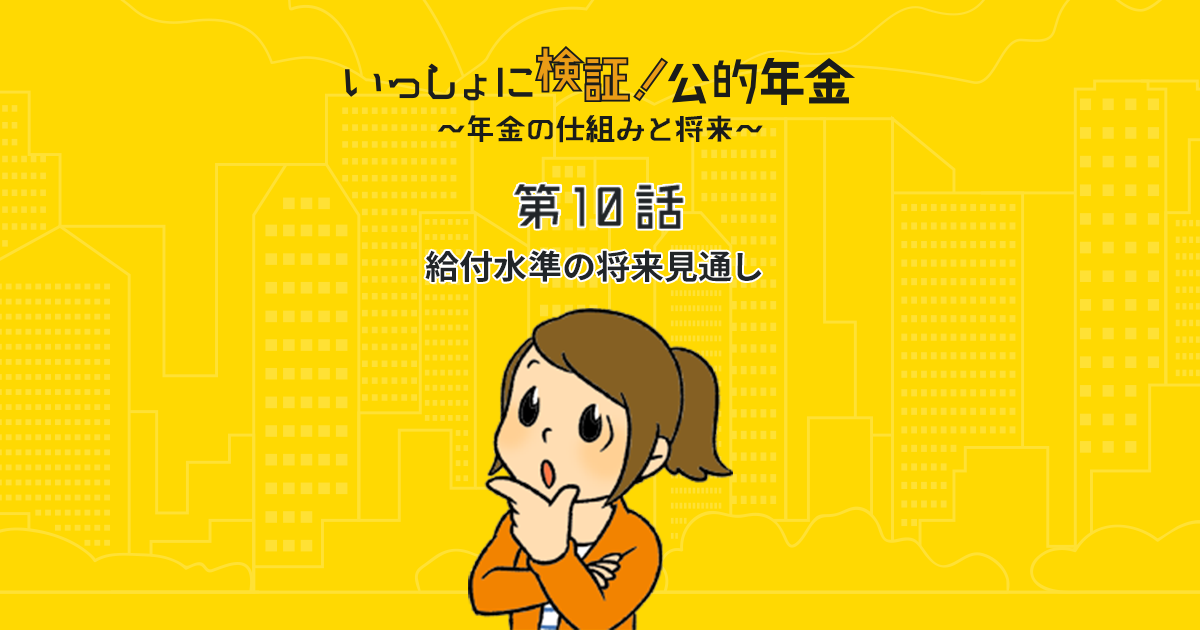
まあ政府の推計は経済見通しや人口推移など、いつも楽観的でよく外れるので、もっと減るだろうなと私は予想しています。
将来はより物価が上がっているでしょうから、物価は上がるが年金は減るという、より厳しい事態に陥る可能性が高いでしょう。
今後は労働人口の減少から、医療や介護などのサービス料はどんどんインフレしていくだろうとの見方が強いです。
以前、老後2000万円問題というものがありましたが、現在では5000万円必要だという声もちらほら聞きます。
年代にもよるのですが、若い世代ほど将来はお金が必要になるでしょうね。
経済産業省も、将来は生産年齢人口の減少が加速していくと予想しています。
また、政府の経済財政諮問会議で、高齢者の定義を65歳以上ではなく、70歳以上にしようとの案が出ました。
私は30代ですが、65歳から年金が受け取れるとは正直思っていません。
私が高齢者になる頃には、下手したら受給開始が80歳とかになっているのでは?年金には不信感しかありません。
このままいくと、80歳になっても働かないといけない社会になっているのかもしれません。
つまり、今後どうなるか分からない年金を当てにするのではなく、個人でしっかり資産形成して老後に備えないといけない時代になってきているのです。
そもそもNISAやiDeCoなどの制度拡充や、政府が掲げる「貯蓄から投資へ」のスローガンは、
年金を満足に支給できないことへの裏返しとしか思えません。
よって、投資をしないという選択をするのなら、一生労働し続ける覚悟をもたないといけません。
■リスク分散(日本円の信用低下、日本の経済力低下、人口ピラミッドを載せる)
投資をしないといけない3つ目の理由は、リスク分散のためです。
さて、皆さんは日本円を信用していますか?
いきなり何を言い出すんだ?と思うかもしれませんが、今後本当に日本円は大丈夫なのかと警鐘を鳴らしたかったのです。
前述の通り、今後はかなり高い確率で少子化や高齢化が進み、人口も減っていきます。
日本はいわゆる人口オーナスの状態になってしまっています。
人口オーナスとは、少子高齢化により生産年齢人口(15~64歳)の割合が低下し、社会保障費の負担が増加することで経済成長を阻害する状態です。
人口オーナスには、以下の特徴があります。
- 経済の重荷となる状態
- 働く人よりも支えられる人が多くなる社会
- 労働力人口が減少し、社会保障制度そのものを維持することが困難になる
- 社会保障費などが重い負担となるため、消費や貯蓄、投資が停滞する
先進国はみんな少子化ですし、高齢化も進行していますが、日本は殊更ひどい状況です。
出生率は以下の記事によると、227カ国中212位。

高齢化は227カ国中2位です。

その結果、日本の潜在成長率は低い。今後はあまり成長しないと評価を受けています。
短期的には分かりませんが、長期的に見ると投資したいと思えるような国だとは思われにくいでしょうね。
https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp2023_gaiyou.pdf https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/2050_keizai/pdf/001_04_00.pdf今後大きく移民政策に転換する可能性もありますが、インドやイランですら少子化になってしまっていますので、日本に移民が来てくれるか分かりませんしね。
今後少子化が加速する中で、世界はAIやロボットで自動化を推進していくのではないかと予想していますが、日本は残念ながらデジタル後進国。
自動化の普及も遅いんだろうなと絶望を感じています。
また、悪いことに日本政府はとんでもないほどの債務を抱えています。
世界ではトップクラス。先進国でもダントツです。
その結果、日本国債の信用は先進国でも最低です。
ということは、今後日本は衰退の一途をたどる可能性があるということです。
皆さんもなんとなく予想しているかと思いますが、日本の将来はあまり良いものではないでしょう。
さて、貯金は言い方を変えると、日本円への100%集中投資です。
投資をしないということは、今後衰退の可能性が高いにもかかわらず、日本円に依存せざるを得ないということです。
日本円が今後大幅に価値棄損したらその影響をもろに受けてしまいます。
このように、投資をしないリスクというものも当然あります。
いわゆるリスクを取らないリスクというやつですね。
日本人はリスクを取らないことが正しいと思ってるきらいがありますが、リスクは取りすぎることも問題ですし、逆に取らなすぎることも問題です。
あくまでリスクはバランス良く適切に取ることが大事なんです。
なんなら、日本円しか保有していないということは、今後衰退の可能性が高いことを考慮すると、逆にリスクを取りすぎてると言えるかもしれませんね。
現状ではまだ大丈夫だと思いますが、今後はそう言われてもおかしくありません。
現在の日本でも将来に対する悲壮感が漂っているように感じます。
10年後はもっと悲壮感が漂っていると思います。
20年後はもっともっと悲壮感が漂っているでしょう。
30年後はもっともっともっと悲壮感が漂っているはず。
そのような状況だと、あれ?このまま日本円持ってるとヤバくない?と日本円を見限る国民もどんどん出てくる可能性があるのです。
少なくとも私は日本円を信用しきれないので、資産は基本的に米ドル建てです。
私は衰退していく国の通貨よりも、成長していく国の通貨を持ちたい。
そして、通貨だけでなく、株式や債券やゴールドなどにリスクを分散したいです。
【投資をするメリット】
■お金が増えるかも
ある程度の経済力と自由を手に入れるためには、投資はほぼ必須です。
圧倒的な所得があれば、そうでもないですが。
■リスク分散ができる
■金融リテラシーの向上
長期投資はプラスサムゲーム
リスクを取らないリスクもあるし、この世にゼロリスクなど存在しない
近年は投資格差という言葉も出てきた

・失敗を恐れてはいけない
失敗しないことより挑戦しないことがよりリスクが大きいかもしれない
投資をしないリスクもあるし、失敗したってまたやり直せばいい。トライ&エラー
・投資って何百万勝った!とか何千万負けた!とかそんなイメージあるかもしれないけど、
やり方によって全然違う
ハイリスクハイリターンなリスク選好なやり方も、ローリスクローリターンな堅実なやり方もある
・貯金も投資も両方やればいい
別にいまあるお金全てを投資に回せと言ってるわけではない
資産の10%でもいいし、なんなら1%でもいいから投資をやってみれば?
10万円からでもいいし、1万円からでも始められる
・資産が少ないから投資をやらない?
逆だよ!資産が少ない内から投資を始めよう
・投資しなければ、時間や労力を対価として払い続けないといけない
・お金は、経営者や社員に働いてもらって増やせばいい
株式投資をしたら自分のために働いてくれるんだよ?
・マネタリーベースやマネーストックは基本的に増えていくので、その分金融商品に資金が流れやすい
・政治家や財務省や日銀に文句言うくらいなら、各自しっかり備えておこう
日本円だけでなくドル建て資産を保有したり
・恐らく、今後の先行きの不透明感は増すのではないか
世の中の複雑性は増加し、AIの登場によって職も危ぶまれる
・為替を動かす要因は様々
為替は短期的だと経済政策や経済指標などで動くが、長期的(大局的)にみると国力で動くと言ってもいい
そのため、日本円は長期的には円安方向へ動く可能性が高いと思う
【まとめ】
今後は投資をしている人と、していない人とでどんどん格差が広がっていくでしょう。
近年の株高もあり、家計資産は大きく増えたようです。
いつの間にか富裕層になっていたという人も増えたとか。
日本の家計金融資産は過去最大

いつの間にか富裕層

投資をするのもしないのも自由ですが、投資をしない選択をするならずっと労働を続けないといけない。
残念ながら、この考えは持っておかないといけません。
私は投資をして、自分だけでなく、お金にも働いてもらうことを推奨しています。
私は米国株中心ですが、アップルやマイクロソフトなど色々な会社に投資しています。
これらの会社に投資をするということは、株価上昇のために優秀なアップルの社員やマイクロソフトの経営者や社員に働いてもらっているということです。
確かに、投資経験がない方だと多少なりとも投資に対する不信感があるかと思います。
そこで、まずは投資について勉強することから始めましょう。
本ブログでも投資に関する情報発信に努めますので、ご覧いただければ幸いです。
勉強した結果、投資をしない決断をしても全然構わないのです。
まずは知ることから。これが大事なんです。
新NISA口座数が急増! 1年で17%増

日本経済は30年以上もの間停滞してきました。
その原因は政府にも日銀にもあったでしょうし、国民にもあったことでしょう。
ですが、文句を言ったところでどうにもなりません。
一時的に溜飲が下がるだけで現実は変わらないのです。
人や世間は変えられない。
では、自分が変わるしかない。
もし今後お金に困りたくないと思うのなら、やはり投資をしましょう。
■資本家に回ろう
・資本主義社会では、どうしても労働者側より資本家側の方が強い
・トマ・ピケティのr>g
・基本的に年々物価は上がる、会社は大きくなる、資産や投資額も大きくなる。お金の循環でできるこの流れが資本主義なんだと思う。
なので、現金でずっと持っていると、大きくなる流れに乗れない。
その考えでいくと、個人的にはたくさん投資され、大きくなる会社を選択、投資している投資信託は労力の割に増やせると思う。
・2040年代から、日本はマイナス成長に陥ってしまうとの政府予想も…
投資をするしないなんて、もちろん皆さんの自由です。
しかし、選択には結果が伴います。
現行制度のままでは、若い世代ほど「支払う額 > 受け取る額」になる傾向が強まります。
すでに支給開始年齢の繰り下げや、支給額の実質的な減額(マクロ経済スライド)も行われています。
今後は70歳支給開始が標準化する可能性も十分あり得ます。
—
2. 医療・介護費は増加 → 利用者負担が増える
高齢者人口の増加で、医療・介護にかかる費用は急増中。
高齢者も含めた自己負担割合の引き上げが今後進む見込み(すでに一部では2割・3割負担が導入)。
医療制度も、「予防重視」「地域医療強化」などにシフトせざるを得ません。
—
3. 税と社会保険料の増加は不可避
少子化により現役世代が減る一方で、支えなければならない高齢者は増える。
結果として、現役世代の負担(消費税・所得税・保険料など)は今後も増える可能性が高い。
投資はお金を活かす行為です